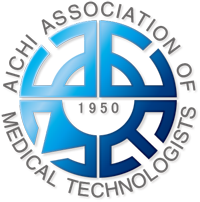よくあるご質問

手続きについて
-
愛臨技ホームページの求人情報掲載については、愛臨技会員の相互扶助を目的に行っており、基本的に会員からの掲載依頼とさせていただいております。但し、会員がいない施設でも掲載を希望される場合は、「採用臨床検査技師に対し、生涯教育のために入会を勧めること」を条件として、掲載許可とさせていただいております。趣旨をご理解いただき、掲載を希望される場合は件名に「求人票掲載希望」と記載の上、技師会事務所までお問い合わせください。折り返し連絡させていただきます。
-
「各種手続き」画面内(→ こちら)の共催・協賛・後援申請書(他団体からの申請用)をダウンロードし、様式内に記載の必要書類とともに愛臨技事務所まで提出(郵送、メール添付、FAXいずれも可)してください。
-
下記ガイドラインを参照の上、日臨技へお問い合わせください。
愛臨技HP会員サイトについて
-
会員サイトにログイン後、右上に表示されるお名前をクリックすると、会員管理ページに移動します。『プロフィールを編集』―『登録情報の編集』からお願いいたします。
なお、愛臨技H Pシステムでは1アドレスに対して1名しか登録できません。職場などの共有アドレスを登録される場合はご注意ください。
また、愛臨技H Pと日臨技会員サイトは別のシステムです。施設名、登録アドレスを変更される場合は、お手数ですがそれぞれ登録内容変更をお願いいたします。 -
初期登録アドレスは、日臨技会員サイトに登録されているアドレスです。
但し、ご自身で愛臨技H Pの会員情報へ別のアドレスを登録されている場合もありますので、ご注意ください。また、職場の共有アドレスを登録している場合、愛臨技H Pへの登録ができていない場合があります。その場合は、お手数ですが技師会事務所までお問い合わせください。 -
会員サイトの初期パスワードは生年月日の西暦表示 8桁の数字です。
パスワードの変更をされていて、忘れてしまった場合はお手数ですがパスワードのリセットをお願いいたします。
愛臨技活動について
-
会員に対してのお知らせメールは、日臨技会員サイトに登録されたアドレスに配信されます。配信元アドレスは jamt_pref23@sys.jamt.or.jp です。
迷惑メールフィルタなどの設定をされている方は、受信設定をお願いいたします。
またお使いのメールサイトによっては、多数の宛先に一度に送信されるメールを迷惑メールと判断する設定となっていることもあります。
毎月配信されている、らぼニュース配信のお知らせメールが届いていない会員におきましては jamt_pref23@sys.jamt.or.jpからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。なお、一部のキャリアメールでは添付ファイルサイズが大きい場合、添付ファイルが削除された状態で送信されているようです。可能であればキャリアメール以外のアドレス登録をお願いいたします。
タスク・シフト/シェアについて
-
直腸肛門機能検査の範囲は、”バルーン及びトランスデューサーの挿入 (バルーンへの空気の注入を含む)並びに抜去を含む”が臨床検査技師の業務範囲となりますので、臨床検査技師が直腸指診など指を入れて確認する行為は、法的に業務範囲外となります。
-
今回のタスク・シフト/シフティングでの内視鏡検査での臨床検査技師の業務範囲につきましては検査のために内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取し、病理組織検査を実施し、良性か、悪性等の治療行為の判断等を行なうものであり、当該判断等により、組織全体を乗り除くポリペクトミー等については、治療行為の一環と考えられますので、今回、法改正により認められた行為を超えていると考えることから、実施できないとなります。
-
今回追加された業務である超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為において、造影剤の種別の指定はありません。
「コントラスト剤として自己血、生理食塩水、空気で作成したもの」は循環器・脳外科領域でしばしば用いられる方法です。投与する方法は今回の追加された行為と同様ですので問題ないと思います。
生理食塩水を用いる造影は空気と混ぜあわせてバブルを作成して注入します。バブルは肺を通過せず心エコー領域(循環器、脳外科依頼)で多く使用されています。ある意味、今回名前が出ている超音波造影剤のソナゾイドも微小気泡からなる造影剤です。生理食塩水を満たしているラインを通してソナゾイドを注入します。
唯一承認されている造影剤がソナゾイドであるため指定講習会ではソナゾイドを用いています。今後新たな承認薬剤が出てくれば当然実施可能となります。
また、それ以外の造影剤に類するものについても手技や投与方法に差異が無ければ実施可能と思います。
造影剤に類するもの安全性や効果等についての議論は別の問題になります。 -
「採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為」
成分採血装置の操作については、以前より実施施設の半数で、臨床検査技師による操作が行われておりましたが、この行為自体が本来違法であったため、今回の法改正要望として諮り、臨床検査技師による実施が認められました。
また、採血を行う際、末梢静脈路の血管確保の業務が実施可能となったため、成分採血装置の接続も可となりました。しかし、自己血貯血の行為については今回認められていませんので臨床検査技師は実施できません。 -
残念ながら今回の法改正では実施できません。
針筋電図は診断しながら検査を進めていく内容となりますので、検査技師には許可されていません。